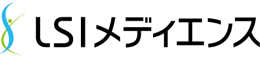WEB総合検査案内 掲載内容は、2025 年 12 月 1 日時点の情報です。
| 項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04107 |
尿中アルブミン 〈クレアチニン補正〉albumin3A015-0000-001-061 |
|
25 |
8週 冷蔵 |
TIA | mg/g・Cr 13.6 以下 |
99 D001 8 尿便 |
2~3日 |
| 項目 コード |
検査項目 |
|---|---|
04107 |
尿中アルブミン 〈クレアチニン補正〉albumin3A015-0000-001-061 |
| 採取量(mL) 遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 |
|---|---|---|---|
|
25 |
8週 冷蔵 |
TIA |
| 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要 日数 |
|---|---|---|
mg/g・Cr 13.6 以下 |
99 D001 8 尿便 |
2~3日 |
備考
参考
- 総合検査依頼書のマークチェックで依頼可能な項目です。
診療報酬
- 保険名称:尿中特殊物質定性定量検査/アルブミン定量(尿)
- 実施料:99
- 診療報酬区分:D001 8
- 判断料区分:尿・糞便等検査
「尿中トランスフェリン」、「尿中アルブミン」、「尿中Ⅳ型コラーゲン」は、糖尿病患者または糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期または第2期のものに限る)に対して行った場合に、3月に1回に限り主たるもののみ算定できます。
検査項目解説
臨床的意義
試験紙法で検出されない微量の尿中アルブミンを定量。腎糸球体障害、とりわけ糖尿病性腎症の早期発見に有用。
糖尿病の三大合併症の一つとして糖尿病性腎症が知られている。従来、この診断には試験紙による尿蛋白の定性検査法が広く用いられてきた。しかし、尿蛋白定性検査が陰性でも、すでに腎の組織学的変化が始まっている場合が多く、陽性が認められる頃にはかなり進行している症例が少なくない。
尿中アルブミンは、腎糸球体障害の進行に伴い尿中排泄量が増加する物質である。本検査は尿中微量アルブミンとも呼ばれ、試験紙法で検出される以前の軽度腎障害を判定できる利点をもつ。
尿中アルブミンの測定法自体は30年以上前、すでに開発されておりTIA法などの簡便な測定法が実用化を見るに到った。一般に尿試験紙の感度は300μg/mL程度であるが本法では1μg/mL程度まで検出できる高感度な測定系であり、糖尿病による糸球体の病変を早期に検出することが可能である。腎症の早期発見により適切な処置を講ずれば、重度の腎障害や人工透析への進行を遅らせることが可能と考えられる。
結果の評価に関してはアルブミン排泄率(albumin excretion rate:AER)がよく用いられる。AERはμg/min.で表わされ、通常24時間蓄尿し、それを1分当たりの量に換算することにより求められる。厚生労働省糖尿病調査研究合併症班の基準によると24時間蓄尿では15μg/min.以下が正常とされている。
【高値を示す疾患】
糖尿病性腎症,ネフローゼ症候群,糸球体腎炎,ループス腎炎
関連疾患
E14.2.3:糖尿病性腎症 → E10-E14:糖尿病
N04.9.3:ネフローゼ症候群 → N00-N08:糸球体疾患
N05.9.1:糸球体腎炎 → N00-N08:糸球体疾患
N08.5.1:ループス腎炎 → N00-N08:糸球体疾患
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.