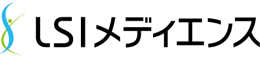WEB総合検査案内 掲載内容は、2025 年 12 月 1 日時点の情報です。
| 項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00311 |
クリオグロブリンcryoglobulin5A160-0000-023-096 |
遠心
|
01 |
4週 冷蔵 |
ゲル内拡散法 | (-) |
42 D015 5 免疫 |
4~5日 |
| 項目 コード |
検査項目 |
|---|---|
00311 |
クリオグロブリンcryoglobulin5A160-0000-023-096 |
| 採取量(mL) 遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 |
|---|---|---|---|
遠心
|
01 |
4週 冷蔵 |
ゲル内拡散法 |
| 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要 日数 |
|---|---|---|
(-) |
42 D015 5 免疫 |
4~5日 |
備考
検体
- 採血後、速やかに血清分離して保存してください(血清分離までは37℃保存)。
- 血清分離の際は、冷却遠心を避けてください。
診療報酬
- 保険名称:血漿蛋白免疫学的検査/クリオグロブリン定性
- 実施料:42
- 診療報酬区分:D015 5
- 判断料区分:免疫学的検査
参考文献
Okazaki, T. et al.: Clin. Chem. 44, (7), 1558, 1998.
検査項目解説
臨床的意義
冷却により可逆的な沈降性を示す異常蛋白。クリオグロブリン血症および膠原病等の免疫疾患で検出される。
クリオグロブリンは血清を冷却(通常は4℃)すると白濁またはゲル化し、37℃に戻すと再溶解する異常タンパクである。
単一の免疫グロブリンである場合と、複数のタンパクによる場合があり、前者は多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症など、後者はSLEや慢性肝炎などで認められる。原因別にみると基礎疾患に随伴する続発性と本態性クリオグロブリン血症に分けられる。本態性のものにはLoSpalluto-Meltzer症候群と呼ばれるまれな疾患があり、随伴する可能性のある全ての基礎疾患を否定することにより診断される。一方、続発性のものには多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症、膠原病、慢性感染症などが挙げられる。
冷蔵保存で血清検体が白濁したり、レイノー現象などが見られた場合には、クリオグロブリンの検索を行なう。単一クローンによる場合は、免疫電気泳動によりM蛋白の同定が可能である。ただし、M蛋白の存在がそのままクリオグロブリンの存在を意味する訳ではないので注意が必要である。
なお、クリオグロブリンが陽性の場合、定量を目的にクリオクリットを測定する場合がある。血清をWintrobe管(血沈管の一種)に目盛り10まで入れ4℃で保存し沈殿物が生じたのち3,000rpmで30分間、冷却遠心を行いクリオグロブリンの沈殿層の高さにより全体に対するパーセンテージをみるが、通常衛生検査所では検査されていない。
温熱により沈降性を示すタンパクをパイログロブリンと呼び、悪性のM蛋白血症で認められることがあり、免疫電気泳動が有用である。
【陽性を示す疾患】
多発性骨髄腫,リンパ性白血病,サルコイドーシス,本態性クリオグロブリン血症,急性心筋梗塞,慢性肝炎,肝硬変症,関節リウマチ,シェーグレン症候群
関連疾患
C90.0.5:多発性骨髄腫 → C81-C96:リンパ組織・造血器腫瘍
C91:リンパ性白血病 → C81-C96:リンパ組織・造血器腫瘍
D86.9.1:サルコイドーシス → D80-D89:免疫機構の疾患
D89.1.11:本態性クリオグロブリン血症 → D80-D89:免疫機構の疾患
I21.9.5:急性心筋梗塞 → I20-I25:虚血性心疾患
K73.9.2:慢性肝炎 → K70-K77:肝疾患
K74.6.13:肝硬変症 → K70-K77:肝疾患
M06.9.2:関節リウマチ → M05-M14:炎症性多発性関節疾患
M35.0.1:シェーグレン症候群 → M30-M36:全身性結合組織疾患
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.