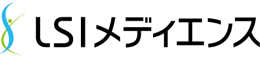WEB総合検査案内 掲載内容は、2025 年 12 月 1 日時点の情報です。
| 項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00601 |
尿中一般物質定性半定量検査 蛋白定性protein, qualitative [urine]1A010-0000-001-911 1A010-0000-001-911 |
|
25 66 |
冷蔵 冷蔵 |
試験紙法 | (-) |
1~2日 |
| 項目 コード |
検査項目 |
|---|---|
00601 |
尿中一般物質定性半定量検査 蛋白定性protein, qualitative [urine]1A010-0000-001-911 1A010-0000-001-911 |
| 採取量(mL) 遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 |
|---|---|---|---|
|
25 66 |
冷蔵 冷蔵 |
試験紙法 |
| 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要 日数 |
|---|---|---|
(-) |
1~2日 |
備考
容器
参考文献
今井宣子, 他: 機器・試薬 8, 97, 1985.
島田 勇, 他: 機器・試薬 9, 959, 1986.
太子 馨, 松岡 瑛: 検査と技術 18, 1451, 1990.
伊藤機一, 野崎 司: 日本臨牀 57, (増), 45, 1999.
検査項目解説
臨床的意義
尿中の蛋白量を測定し、腎疾患の早期発見や治療効果をみる検査。
腎泌尿器系疾患のスクリーニングに用いられるもっとも基本的な検査のひとつである。
尿蛋白の測定には、一般に試験紙法による半定量がスクリーニングに用いられる。しかし、タンパクの種類により感度が異なるため、ベンスジョーンズ蛋白のスクリーニングや腎不全患者での経過観察には本法のような定量検査が必要となる。
生理的条件下での蛋白尿には次のようなものが知られている。過激な運動、精神的ストレス、多量の肉食、熱い湯での入浴後、月経前などに生理的蛋白尿が一過性に出現する。起立性蛋白尿は小児に多くみられ、起立時に出現し安静臥床にて消失することが知られている。しかし、これらはいずれも一過性で、タンパク量も少ない。
腎疾患以外の病態でみられる蛋白尿には、発熱時や黄疸に認められる熱性蛋白尿、尿路の炎症による血液・膿・粘液などの混入にもとづく仮性蛋白尿、多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症によるBence Jones蛋白,溶血や筋肉崩壊に伴うヘモグロビン尿,ミオグロビン尿などの特異な蛋白尿が知られている。
一方、本来の腎疾患(糸球体腎炎、ネフローゼ症候群など)による蛋白尿を腎性蛋白尿といい、糸球体性蛋白尿と尿細管性蛋白尿に分類される。いずれも持続的かつ比較的高濃度な蛋白尿であるが、糸球体性蛋白尿以外では蛋白量が病勢と必ずしも一致しない。
一般に糸球体性蛋白尿では腎糸球体の選択的蛋白透過性の喪失により、アルブミンなど分子量の小さいタンパクからIgGなど比較的大きいタンパクまで広範に認められる。
蓄尿の際には、正確に全量を測りとる必要がある。
【陽性を示す疾患】
糖尿病,アミロイドーシス,膠原病,IgA腎症,ネフローゼ症候群,糸球体腎炎,腎不全,尿毒症,腎硬化症
関連疾患
E14.91:糖尿病 → E10-E14:糖尿病
E85.9.1:アミロイドーシス → E70-E90:代謝疾患
M35.9.3:膠原病 → M30-M36:全身性結合組織疾患
N02.8.1:IgA腎症 → N00-N08:糸球体疾患
N04.9.3:ネフローゼ症候群 → N00-N08:糸球体疾患
N05.9.1:糸球体腎炎 → N00-N08:糸球体疾患
N19.3:腎不全 → N17-N19:腎不全
N19.4:尿毒症 → N17-N19:腎不全
N26.4:腎硬化症 → N25-N29:その他の腎・尿管の疾患
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.